地下鉄サリン事件とパソコン通信が照らしたメディアの未来

地下鉄サリン事件が映し出した、情報社会の転換を事件を通して考察します。
弊社が数ある菓子問屋から少し変わった特徴ある会社へと変化するきっかけとなったのは1995年3月20日、東京の地下鉄を襲った、地下鉄サリン事件でした。この事件は新たな恐怖の時代を告げただけではなかったように感じます。それは、情報社会におけるメディアと国家、信仰とテクノロジーの関係を根底から揺るがす事件でもありました。
この事件の影にあったもう一つの顔——それは、オウム真理教というカルト集団が、奇妙なほどに“先端”を志向していた事実です。彼らは単なる宗教団体ではありませんでした。自前のコンピューター開発室を持ち、秋葉原や名古屋の大須にパソコンショップを構え、パソコン通信の掲示板を使いこなしていました。公安当局が杉並支部に突入したそのとき、支部の一信者はニフティサーブにログインし、掲示板で状況を“実況”していたのを私自身が偶然リアルタイムで見ていました。
これは、単なるカルトの逸話ではないのです。ここには、20世紀末におけるメディアの変質、つまりマス・メディアからインタラクティブ・メディアへの地殻変動が刻まれています。サリン事件の背後で進行していた“情報革命”を、私は偶然体験することで次の消費へのキーワードとなる新たな「鍵」を手にし、ネットで物が売れる時代へ向けて、わずかですが先取りできたことが、他の問屋との一線を画す契機になったと思っています。
そんな私が、パソコンのネットワークは「インターネットになりメディアになったから、ものが売れる」という単純な話ではなく、当時を振り返りながらもう少し深掘りしてみました。
オウムと秋葉原:カルトとテクノロジーの奇妙な共鳴

1990年代初頭、秋葉原や名古屋の大須ははただの電気街ではなかったと思います。一部の若者たちにとって、それは「未来の道具」が集まる都市の最前線でした。自作パソコンの部品、電子工作キット、DOS/Vマシン、CD-ROM——それらは手の届くかたちで近未来を約束していたのです。
その一角に、「オウムPCショップ」は静かに存在していました。外見は普通の小売店と変わらず、PCマニアや学生たちが自然に吸い寄せられていく。とにかく激安だったことを覚えています。カルト宗教とITが結びつくなど、当時の誰が予想できたでしょうか。しかし、オウム真理教は真剣にコンピューターとその可能性を追求していたようです。
内部では教団構成員が自らPCの組み立て、OSインストール、販売業務を担っていたことが後ほどわかりました。その労働は精神修行であり、技術的熟達は「真理への接近」という位置付けだったようです。情報社会が宗教的な意味を帯びる、奇妙な先取りがそこ見て取れます。
掲示板という“もう一つのメディア空間”
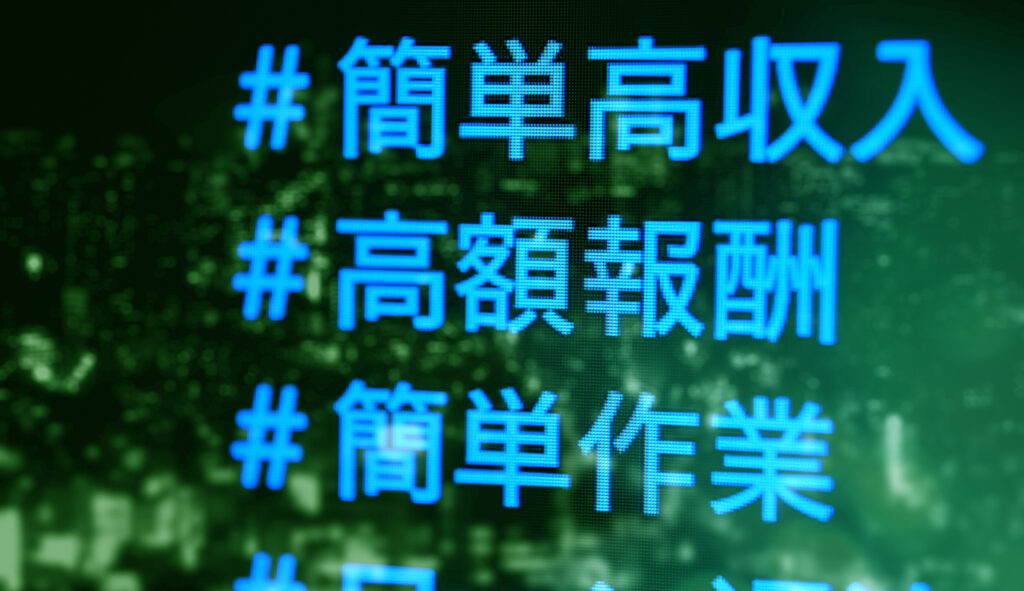
地下鉄サリン事件が起こった後、1995年3月22日、警視庁公安部が杉並支部に突入したとき、そこにいた信者の一人が取った行動は、全く持って予想を裏切るものでした。彼はニフティサーブの掲示板にアクセスし、「公安が来た」「今、ドアを壊そうとしている」と書き込んでいたのです。ニフティーサーブの掲示板で、異常に閲覧者数が多く、リロードするたびにその閲覧者数と書き込み数が莫大に伸びていく掲示板を見つけた私が、リアルタイムで見た事実です。
これは些細な逸話のように見えて、パソコン通信というメディアの本質を暴いているようで、振り返ると象徴的です。
パソコン通信とは、1970年代から80年代にかけて日本で発展した、文字による通信ネットワークです。電話回線にモデムを接続し、各種のBBS(電子掲示板)にアクセスする。そこでは、新聞もテレビも報じない情報が飛び交い、“ユーザー”たちは能動的に書き、読み、応答していました。
文字だけで構成されたこの空間は、当時、テレビや新聞とは異なる「現実」を描く舞台でした。匿名性、即時性、参加性——掲示板はマスメディアとはまったく違う論理で動いていました。誰でも書き込める。誰でも読み、反応し、スレッドを形成できる。そこでは“情報”が一方的に提供されるものではなく、協働的に編まれるものでした。

ビジネスフォーラム、宗教フォーラム、サブカルチャーフォーラム、政治議論板。多くのトピックが立ち上がり、そして沈んでいく。その「短命な言説の流通」は、今思えばインターネット時代の予兆だと断言できます。
オウム真理教の信者たちは、自分たちの教義や活動をパソコン通信を通して外部に発信していました。その書き込みは、マスコミに圧倒的に不利な印象で報じられる中で、「自分たちの真実」を語る空間として機能していました。ここに、後のSNSやYouTubeが持つ「自己編集された現実」の原型があると思います。
個人が、あるいは集団が、マスメディアに対抗するメディアを持つことが可能になったとき、情報の価値はどう変化したのか?それは、事実そのものよりも「発信の意志」が重視される時代の到来だったと解釈できます。
この転換は、単にテクノロジーの進化だけではなく、メディアの“構造”そのものの変化でもあります。放送局や新聞社といった「門番」的な存在に頼らずに情報を流通させるモデル。それは、消費社会の変容とも密接に関わって行くことになるのではないか。当時の私はそのようなことをぼんやりと考えていました。
メディアの変容と“参加の時代”の幕開け
事件以降、日本のマス・メディアはオウム真理教を報道対象として“囲い込み”、絶対悪として記号化していきました。一方で、ニフティサーブや草の根BBSには、異なる言説空間が立ち上がっていた。教団の信者や元信者、関係者、疑問を持つ一般人、陰謀論者までが自由に書き込みを行いました。
ここで重要なのは、こうしたBBSが“報道の補助線”ではなく、“独自の言論空間”として機能し始めていた点です。
新聞やテレビは「一対多」の構造を持ち、情報の送り手は限られていました。ですがパソコン通信は、「多対多」のメディアだったのです。そこでは誰もが発信者になりうる。投稿は即座に表示され、他者とスレッドとしてつながる。参加者は“読者”ではなく“当事者”になっていくわけです。
この構造は、やがてインターネットへと引き継がれます。1995年は、日本における商用インターネット元年でもありました。Windows 95の発売とともに、Netscape Navigatorが普及し、HTMLとURLが少しづつPC界隈での日常語になっていったのです。
つまり、サリン事件とパソコン通信の交錯は、情報メディアが“受信”から“参加”へと転換する歴史的ポイントだったのです。
それと同時に1990年代以降、日本社会は「自己表現」と「消費」が限りなく接近していく時代に入っていきました。ブランド志向、キャラクター消費、自己演出としてのファッションやガジェット。そこに登場したのがインターネットであり、個人メディアです。
掲示板やホームページ、のちのブログ、SNSは、「消費者が自己のメディアを持つ」ことを意味していました。カメラ付き携帯、デジカメ、プリクラ、そしてスマートフォンへ。表現と記録の道具は加速度的に個人へと収束し、情報は常に“流通”することを前提に生成されるようになっていきます。

繰り返しますが、この流れの起点に、パソコン通信での情報発信という行為がありました。杉並支部の信者による書き込みは、情報の“価値”ではなく、“所在”を問い直す行為だった。情報がどこにあるのか?誰の手にあるのか?を、如実に表していたのです。
新たなマーケティング
1995年、オウム真理教による一連の事件は「情報」が持つ暴力性と創造性の両義性を突きつけました。しかし、その後の日本社会が歩んだ情報環境の変遷を見れば、オウムが先取りしていたのは、中央集権的メディアから個人主導型メディアへの「構造転換」だったと解釈できます。
オウム真理教は、教義のマニュアル化やビデオ・音声教材を通じて、「知のパッケージ化」を早期に実装していました。これは今日のオンライン教育、eラーニング、動画コンテンツによる知識伝達と構造的に酷似しています。メディアは情報を発信する主体のみによって管理されるものではなく、受け手が選択し、再編集し、共有するサイクルの中に組み込まれるようになった。
この現象は、カスタマージャーニーとブランド体験(Brand Experience)の視点からも読み取ることができます。従来のマス広告モデルでは、メッセージは「発信者→受信者」という直線的な流れで完結していました。しかし、パソコン通信や掲示板による双方向性、そして後のブログ・SNSにおける参加型設計は、顧客(=情報消費者)を能動的な「共創者」へと位置づけ直しました。
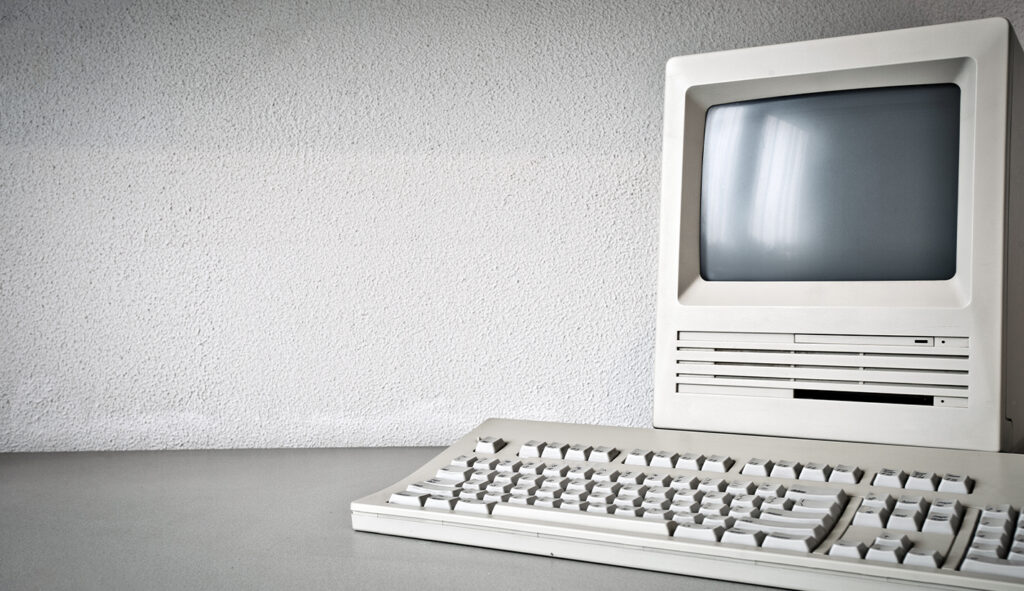
加えて、当時の情報流通はまだナラティブマーケティングの黎明期でした。事件に関する“真実”をマスメディアと異なる文脈で発信することは、オウムにとっての「オルタナティブ・ブランディング」であったわけです。それは自己イメージの構築、共感の喚起、ひいては「支持者とのエンゲージメント強化」という機能すら帯びています。
このような分散型の情報発信モデルは、のちにCGM(Consumer Generated Media)の基盤となり、広告やプロパガンダにおいて「マスメディアを通さずに共感を得る」手法の原型とも言えるのではないでしょうか。
宗教マーケティングからパーソナルブランド消費へ
オウム真理教の情報実践は、典型的な“ブランド宗教”(Branded Religion)ともいえる構造をとっていました。ブランド宗教とは、明確な理念・世界観を持ち、それに共感する者たちがアイデンティティの一部としてその“ブランド”を内面化する現象である。
だが1990年代後半以降、この宗教的帰属意識はパーソナル・ブランドの消費へとシフトしていく。「私はこの理念に従う」から「私はこのキャラ、このコンテンツ、このストーリーが好きだ」へ。つまり、集合的な“信仰”から、選択的で個別的な“愛着”へ移行していったのです。
この転換を説明する上で、ケビン・ロバーツが提唱した「ラブマーク」(Love Mark)理論が示唆的です。ラブマークとは、単なる商品やブランドを超えて、消費者が“情緒的な絆”を持つ対象です。YouTubeの配信者、Twitterの論客、サブカルのキャラクター——彼らは信仰の対象ではありませんが、忠誠や反応という意味で、かつての“宗教的な関係性”と機能的に同質であるように思います。
この文脈において、パソコン通信における「接続」「書き込み」「反応」は、まさにラブマーク的関与の原型と言えるでしょう。人々は教義ではなく、語り口、文体、投稿の頻度、レスポンスの速さといった“体験価値”に反応しています。

やがてこの反応様式は、情報そのものを「消費」する時代へと進化していき、動画視聴、SNSのスワイプ、いいね、リポスト、レビュー。ある種儀式のように反復されるこれらの行為は、行為者自身が「行動を消費する」循環に閉じ込められていきます。
すなわち、宗教性が剥離された情報接触は、純粋なエンターテインメント消費、あるいはセルフブランディングの一部として再配置されたのではないでしょうか。
情報という商品、記号としての未来
いま、私は生成AI、メタバース、Web3といった次の地平に立っている。だがその出発点に、秋葉原のPCパーツ屋や、ニフティサーブの掲示板、パソコン通信のログイン音があることを忘れ宅はありません。
マーケティングの観点から見れば、これは「情報のプロダクト化」の歴史でもあります。情報は単なる伝達手段ではなく、それ自体が“商品”として市場に出回る。信頼性、希少性、拡散性、エンタメ性。これらの属性を備えた情報は、まるでパッケージ化されたブランド商品のように消費者の選別を受けます。
そして、個人もまた“情報としてのブランド”になり得ます。セルフブランディング、自己演出、インフルエンサー経済。これらは、信者ではなく“フォロワー”を獲得するための行為であり、社会がある種自己宗教化していくプロセスとも言えるのではないでしょうか。
未来は不透明であり、情報は依然として暴力にも希望にもなります。しかし、あの時代、オウム真理教が象徴したものとは、ただのカルトではなく、「情報という名の商品」が本格的に市場に登場する、その“前夜”だったのではないでしょうか。








