何も知らない駆け出し経営者が2冊の本から学んだ大切なこと

駆け出し社長が易経と神話から導いた、経営の本質とは。
はじめに
単なる跡取りというだけで、「経営とは何か」など全く知らなかった若造が、曲がりなりにも30年以上にわたって「社長」を務め、なんとか会社を維持継続できたことは、ちょっとした奇跡に近いように思えます。
そんな若造を支えたのが30代初めに出会った2冊の本でした。それはドラッカーでもコトラーでもありません。
- 古典中の古典『易経』
- スターウォーズ好きが高じて読むことになった神話分析に関する本『千の顔を持つ英雄』
この2冊です。
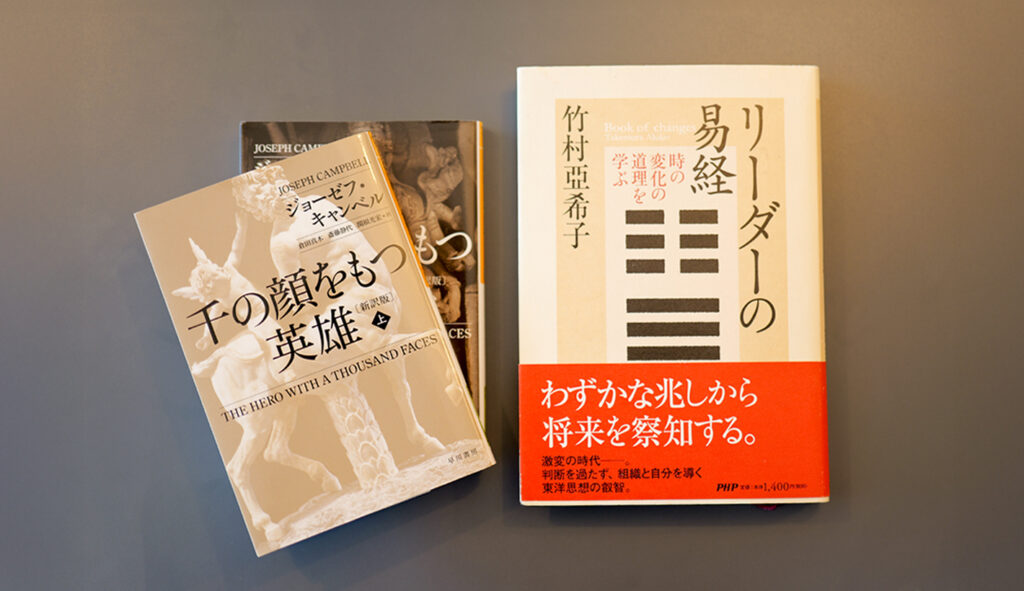
経営学、とりわけマーケティングは、人間の意思決定、行動、文化、そして価値創造に根ざす学問だということをいろんな本を読めば読むほど感じるようになりました。そのため、表層的な手法論や数字以上に、深層的な人間理解が重要なのではないかと考えました。そこにおいて、『易経』とジョーゼフ・キャンベルの『千の顔を持つ英雄』という、一見宗教的・神話的・哲学的に見える書物が、経営において驚くべき洞察をもたらしてくれる。当時の私にはそんな気がしたのです。
足りない地頭で必死に考えた当時を思い起こしながら、この2冊の共通点と相違点を踏まえつつ、それらが株式会社ナカムラの経営戦略、およびマーケティング活動にどのように活かされていくことになったのかをまとめてみました。
『易経』と『英雄の旅』:共通する構造的世界観
変化を前提とした世界観
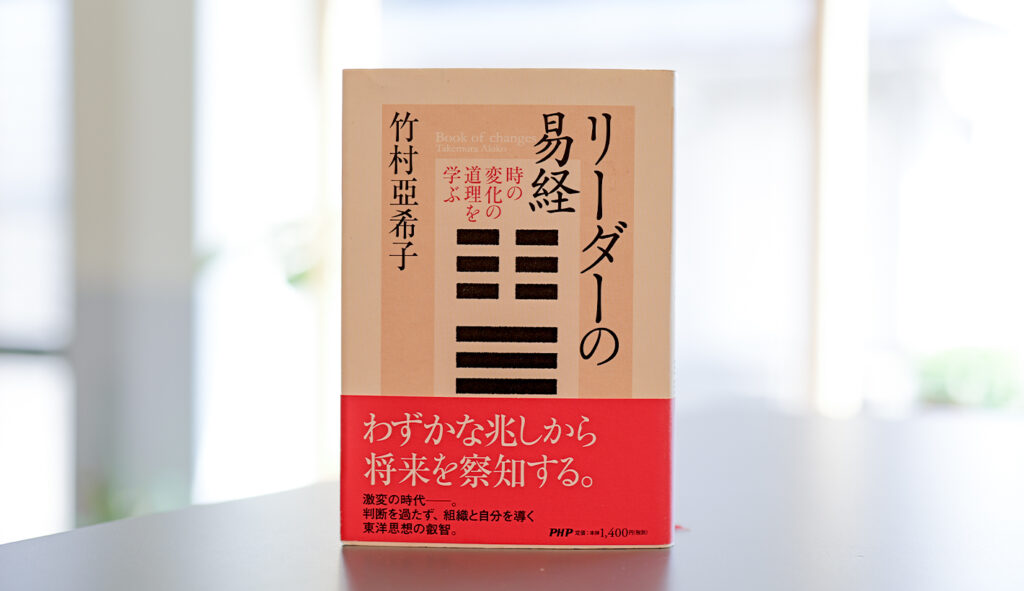
『易経』は、「変化」の書です。英訳はそのものずばり『book of changes』。万物は変化し、すべての事象は陰陽のバランスの中で絶えず移り変わるという思想に貫かれています。六十四卦に表されるさまざまな事象や運命の形は、その変化の相を体系化したものであり、静的な未来予測ではなく、動的な兆候の読み取りが本質であると説いています。
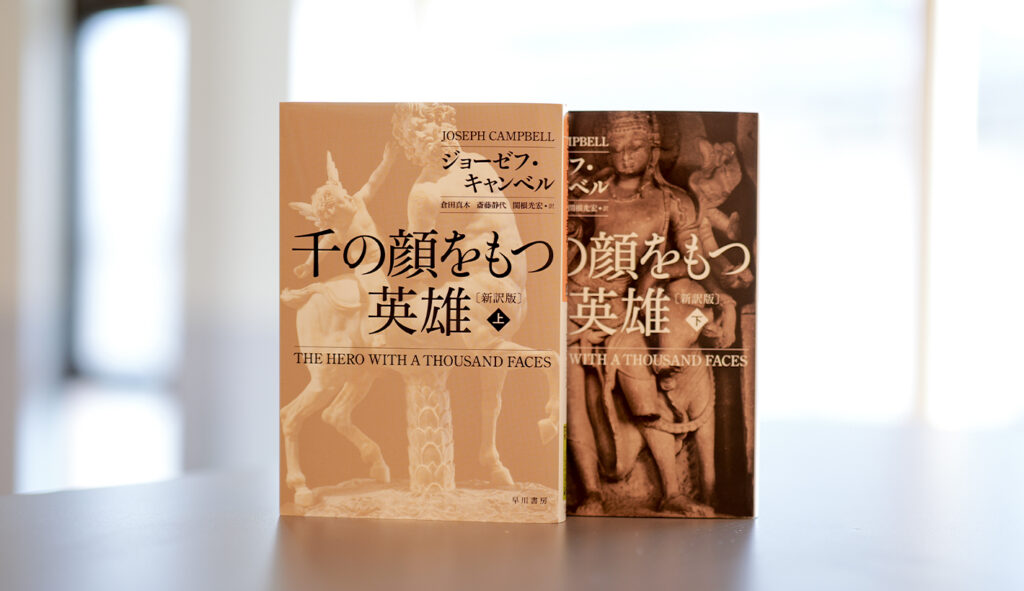
一方、『千の顔を持つ英雄』においてジョーゼフ・キャンベルは、世界中の神話に共通する「英雄の旅(Hero’s Journey)」という構造を抽出しました。それは、呼びかけ→試練→死と再生→報酬→帰還という、変容を伴うプロセスです。この旅は単なる冒険譚ではなく、自己変容の物語であり、常に「前とは異なる自己」へと至る運動であると解釈できます。
両者に共通しているのは、「固定した真理」よりも「変容する真理」を重視している点のように30代の私はとらえました。言い換えれば、現象の本質は流動的であり、そのなかで意味を見出す姿勢こそが重視されると理解したのです。
二元論と統合:陰陽と分岐の統一
『易経』の基本単位である「陰」と「陽」は、光と闇、男性性と女性性、動と静など、あらゆる対立の象徴でありながら、同時に互いに依存し合う補完関係を成しています。この二元論は決して対立を意味しない。むしろ、「陽極まって陰となる」「陰極まって陽となる」というように、対立の中に変化と統合が存在しています。

一方、英雄の旅もまた二元的構造を持っています。日常世界と異界、死と再生、恐怖と克服、秩序と混沌といった二項対立を乗り越える中で、英雄は個人的・社会的な統合を果たしていきます。英雄が「試練」を乗り越えるという構造は、まさに陰と陽の統合・転換そのものに近いように感じられました。
つまり、両者は「対立を乗り越えた先に意味が生まれる」というパターンを共有しているのです。これは、経営やマーケティングにおける葛藤解消やブランド構築にも応用可能な重要な原理だと当時の私はここまで明確ではありませんが、それでもぼんやりと感じました。
経営への応用:「変化」「試練」「統合」の三段構え
戦略的意思決定と「変化の読み取り」
『易経』は「卦」を通じて兆しを読み取り、どのように行動すべきかを示唆する書です。これは現代経営における「シグナル検出」と極めて似ていると思われます。市場の変化、顧客の感情、社会的価値観のシフトといった「兆し」をどれだけ早期に察知できるかが、競争優位を左右するのです。
『千の顔を持つ英雄』における「旅の始まり」もまた、日常生活に現れた異変や「呼びかけ(Call to Adventure)」で始まります。企業もまた、変化を「拒絶」するのではなく、それを「物語」の始まりとして受け入れる感性が必要で、ここが欠けていると人と同様成長が止まるように受け止めました。
したがって、両書に共通するのは「現状維持への固執が最大のリスクである」という警鐘であり、経営においては「戦略的変化受容力」が重要で、進化論同様それこそが持続可能性の原動力だと腹落ちしました。
ブランド構築における「英雄の旅」の活用
現代のマーケティングにおいては、製品やサービスを顧客の「物語」にどう組み込めるかが勝負です。競争戦略が今やストーリーとして語られる時代、キャンベルの英雄の旅の構造は、顧客が「主人公」として自身の人生を物語化するとき、ブランドがどの位置に登場するべきかを指し示す強力なフレームワークとなります。
たとえば、Appleの広告戦略は、常に顧客を「変革を起こす者」として描き、自社製品をその旅の「魔法の道具(Supernatural Aid)」として位置付けています。これはまさに英雄の旅の構造そのものであると思います。
一方、『易経』の「時を待つ」「順を読む」といった概念は、ブランドの成熟、投入タイミング、メッセージ発信の「間」を考える上で重要な補助線となるわけです。つまり、ブランドは「いつ英雄の前に現れるか」によって、その意味合いが変わっていくのです。
リーダーシップと「自己変容の旅」

優れた経営者は、自己の内面においても旅をする英雄でなければなりません。変化の兆しを読み取り、困難な意思決定を乗り越え、組織や社会のために帰還する——これはまさにキャンベルの英雄そのものです。
さらに『易経』では、リーダーとは「天の意志」を読み、それに応じて動く者であり、己の私利私欲ではなく、大義と時勢によって導かれる存在であるとされています。ここでいう「天」は、現代でいえば社会の要請や顧客の声、未来世代の幸福などを指すと考えることもできます。
よって、真のリーダーは単なる意思決定者ではなく、「変化と統合の媒介者」であり、内的変容を通じて外的成果をもたらす存在であるべきなのです。
マーケティング戦略における応用例
ストーリーテリングと物語構造

今日のブランドコミュニケーションにおいては、商品スペックよりも「ブランド・ストーリー」が重視されています。これは消費者が自己のアイデンティティを「物語」によって構築しているからです。ブランドは、その「物語空間」にいかに意味深く参入できるかが鍵となってきます。
英雄の旅をもとにしたマーケティングは、以下のような構造を持ちます:
- 呼びかけ(Needの喚起) :現状への疑問や課題提起。
- 旅立ち(購入の動機付け):ブランドとの出会い。
- 試練(購入・使用体験) :期待と現実のギャップ。
- 再生(感動体験) :成功・納得・シェア。
- 帰還(リピート・伝道) :ブランドの使者となる。
たとえばナイキは「Just Do It」によって消費者の内なる英雄性を喚起し、その旅に伴走するブランドとして機能しています。
顧客インサイトの発見:易経の「兆し」の思想
マーケティングにおいて最も重要なのは、顧客が明示していない「インサイト」を発見する力です。『易経』における「兆しを読む」という姿勢は、このインサイト発見に極めて似ています。たとえば、行動データや口コミの背後にある感情の微細な揺れを読み取り、次の打ち手を導き出すことは、「卦」を読む思考と酷似している。
また、『易経』は「変化に応じて形を変えること」を良しとします。これは、ブランド・マーケティングにおいても重要な示唆です。固定されたメッセージではなく、環境やターゲットに応じて柔軟に形を変え、なおかつ核を失わない。これが「ブランドの持続的進化」の本質であると思われます。

結論:変化と物語の時代における普遍構造の活用
『易経』と『千の顔を持つ英雄』は、いずれも何千年にもわたって人類の文化と意識に影響を与えてきた叡智の体系でもあります。一見、古典や神話というカテゴリに属するこれらの書は、実は21世紀のマーケティングや経営に対しても深い示唆を与えてくれます。
現代のビジネスは、変化と不確実性の中で「意味」を問われる時代です。そのとき、「変化の兆しを読む力(易経)」と、「自己物語を描く力(英雄の旅)」は、企業にとって不可欠の知的資源となると考えました。

これらを経営やマーケティングに取り入れることで、単なる競争優位ではなく、文化的共鳴と長期的な信頼を構築することが可能となり、それはもはや「製品を売る」ことではなく、「生きる意味を提供する」ことに他ならない。そんな仕事がしたい。30代前半の経営者としての基礎を作るべき時期に、この2冊に出会えたことは弊社にとっては非常に意味深いものでした。








