社長歴32年の私がサラリーマンをやってみて感じたこと

経営者が別企業で働いて感じた評価と組織の現実。そこからえた学びをまとめました。
私の社長歴は結構長く現在33期目です。
30歳あたりで、父から引き継いだ会社の社長になったため、こんなに長くやっているわけです。とは言っても年齢的には通常のサラリーマンが定年を迎えるあたりということになります。
ところで表題ですが、「サラリーマンを辞めて社長になって感じたこと」ではなく「社長をやりつつ別会社でサラリーマンをこなして感じたこと」というのがというのが真意です。
54歳からの4年間を自分の会社の社長でありながら、私の会社とは全く別の会社の役員としても過ごしました。非常勤ではなく常勤です(本当です)。
とある会社の役員として「新規事業開発の統括」を任されていました。
この時点ではこれまで私がやってきた仕事が、対外的に評価されて他の会社のオーナーからお声がかかったということになります。

手短にまとめると、社長として、会社の現状を棚卸しし、人、資金、時間という限られた資源の中で社員と会社の未来のために何をして行けば良いのかということを考え実践する日々。
結果として幾つかの失敗を踏まえてそれを糧として新たなチャレンジをし成功を手にする。地味に当たり前のことの積み重ねが、会社の成果と対外的な評価につながったわけです。
お誘いを受けてから2年間ほどはお断りを続けていましたが、事業継承を真剣に考えてみたところ、これはある意味事業継承を円滑に進めるためのチャンスなのかもしれないという気がしてお引き受けすることにしました。(この間の心境の変化についてはいずれ書こうかと思っています)
小さい会社とはいえ当時、25年ほど社長をやってきた私にすれば、役員ではありますがサラリーを出す側ではなく、いただく側になりましたし、私より立場が上な方もいらっしゃいますので、サラリーマンという認識でした。
ここで一番初めに感じたことはこんなことでした。
自分の会社では私が社長であるため、どこまでの失敗や損失であれば目を瞑れる、時間というコストも含めてそういう見積もりをしていました。そういう素地があった上で決断していかないと事業が育つことはありません。
場合によっては10年間ほど耐えながら成長へ導くための努力をすることも当然あります。
ところが、サラリーマンになると我慢したことへの責任が取れないため、どうしても短期間である程度の成果を出さなければならなく、わかっていたことではありますが全く異なる仕事環境となりました。
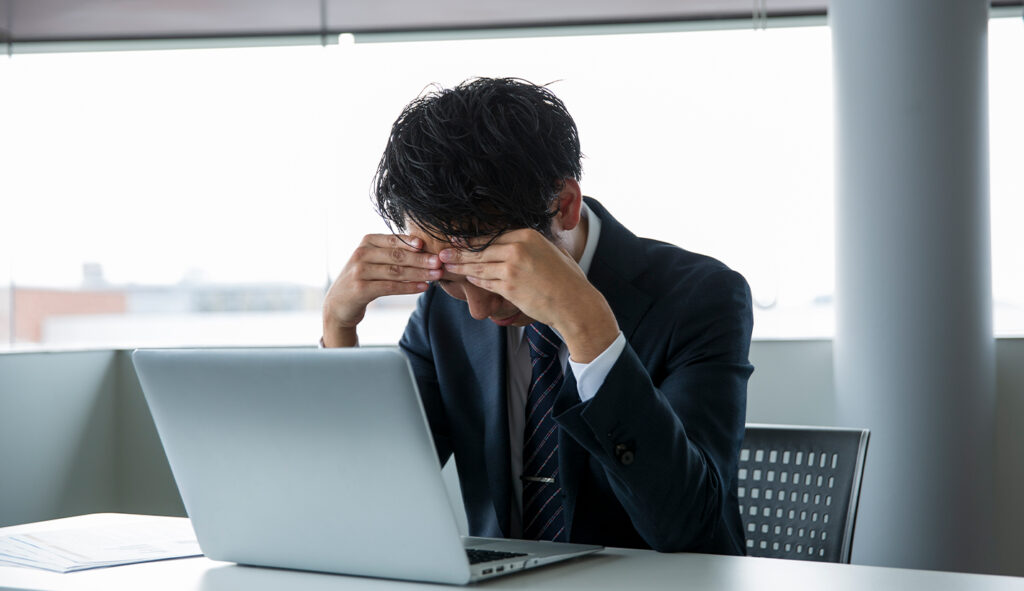
また私の統括するセクションが「新規事業開発」という、短期間で何某かの成果を出せるような分野ではないわけで、引き受けてから改めて今までと違う大変さに気づきました。(お粗末な話です)
売り物もなければ、顧客もいない。そんな全くのゼロベースからのスタートだったからです。
短期間で成果を出すとすると、ギリギリのタイムリミットは多分3年というところでしょうから、3期目が終わった時点で年商50億円規模の会社が新規事業としてまあまあ納得のできる数字を達成することが具体的な私のミッションと捉えました。
いうまでもなく、こんなミッションは深く考え得る必要もなく、置かれた立場で必然的にわかるものですが、わかることとできることは大きく違うわけで実際は大変です。
売るものを作るのに一定以上の時間とコストを必要とし、顧客を見つけるまでにもそれなりの時間とコストを必要とします。
真面目に地道にこんな事をしていたら間に合いうわけがありません。
自分の会社だったらそれこそ地道にやりますよ。でも短期という縛りがあればく、会社や周囲は待ってくれないでしょう。
そこで、モノと顧客を一気に手に入れようと、業務内容を棚卸することで、技術はあるけど工場稼働率がいまいち良くなく、ところが世間的にはこれから伸びてくるんじゃないかというニッチな市場を発見して、うちはこのようなことができますよというわかりやすくはありますが、専門性の高いウェブサイトを作成し、開発案件のリード(見込客)を集めるという手法を取りました。

瞬く間に、狙っていたキーワードでは検索順位の上位を独占し、ニッチな業態ではありますが、ほぼ毎日リードが入ってくる状況になりました。
これって結構な成果だと思うのですが、この時点では会社では全く評価されていませんでした。
「将来のメシのタネ」である開発案件というリードの重要性がその時の会社的には指標にならなかったせいでしょう。
やはりメーカーなので作ってなんぼ、売ってなんぼ、の売上があくまでKPIだったということです。
この辺の詳しい経緯については今回のタイトルテーマから外れますし、詳しく書くと中々の大作になるかと思いますので省きます。
開発案件なんて、問い合わせはあってもの中々実現しづらいものだということはわかってはいましたが、同業種に関わらず、むしろ同業種よりも異業種からのリードが多く、それも国内外を問わずという状況でした。
世界的に知られた企業や、全く無名のベンチャー企業、多くの企業から問い合わせをいただいたことは「潜在需要は確実に存在し、その市場を顕在化できる」という確信に変わりましたが、問題はその時期です。何しろ3年というタイムリミットがあるわけですから。
当時私が率いたスタッフの頑張りで、実現できる案件も増え、リミットと考えていた3年目には2億円余りの売り上げを作ることができました。
チームメンバーに対しては「確かな成果を出すことができた。君たちは胸を張っていい」と当時言った覚えがあります。
ところが・・・。
4年目の終わりで私は退任することになりました。
コロナ禍が始まり、海外関連の案件が全てストップ&キャンセルになったこともありますが、結果的に会社という組織はこの4年間の実績を成果と認めることがなかったというのが真相です。
株式投資などでは当たり前ですが、正比例のように直線的に右肩上がりに成長するなどということはありません。
ある程度の幅の中で上げ下げを繰り返しながら上昇トレンドを描く。というのが一般的な成長というものではないでしょうか?
またオーソドックスな社風の中で、気を衒ったわけではありませんが、新たなマーケティング手法などを駆使して新規事業を組み立てた場合、古くからいらっしゃる会社幹部や役員の理解得られないことが多く、そのため胡散臭さや、一過性という批判に晒されやすいという側面も十分にあるという事を体験しました。
「サラリーマン社会では成果を上げても正しく評価されるとは限らない」
これが社長をしながらサラリーマンをやってみて一番強く感じた事です。

社内政治的な思惑もあるでしょう。ライバル関係や、上司の力関係などなど、さまざまな要因で成果が正当に評価されない。そんな思いを、きっとたくさんの人がしているんだなと。
どんな成果であろうと、それに対応して「良い評価」はもちろん「悪い評価」であっても、正当に評価されると信じて仕事をしてきた社長歴の長い私にとっては驚きの現実でした。
退任にあたり、正当に評価されるべき会社組織にしたいものだと、社長である私自身が思えたのは私の会社としてはとても意味のあることではありました。
しかし、多分多くのサラリーマンの皆さんは、急激には「正当に成果を評価してくれる組織」に変革できる会社に身を置いているわけではないだろうと思います。
だからと言って、私は「起業」「独立」を進めるものでもありません。
大切なのはバランスです。
たとえ成果を上げても正当に評価がされないのが会社であれば、そのストレスを軽減するためにも一か八かの起業や独立をするのではなく、会社という組織に帰属しながら「成果が正当に評価される状況に身を置く」そうして心のバランスを保つことが大切な気がします。
具体的にそれが何かとは一概に言えませんが、趣味の世界や、資格取得に向けた勉強なのかもしれません。
会社という組織の中では正当に評価されなくても、別のコミュニテーでの成果や評価の積み重ねがある種の資産となることもあるでしょう。
それがもしかしたら「起業」「独立」の礎になるかもしれません。
ビジネスマン人生の中のほんの短い4年というサラリーマン時間でしたが、とても大切な事を教えてもらったと思っています。









